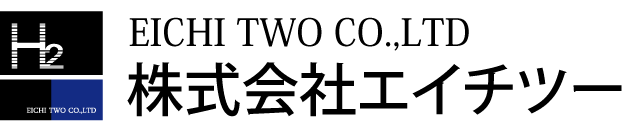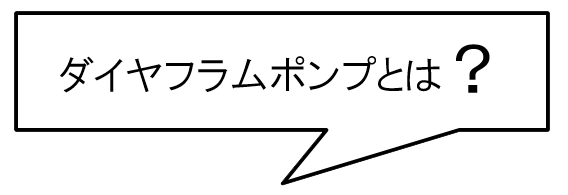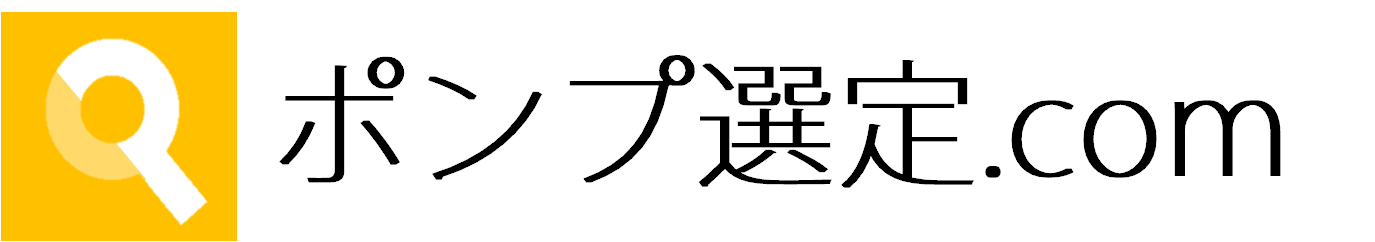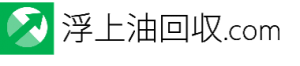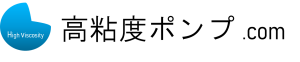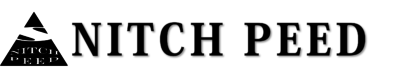FROM:長谷
祝日も合わせて4連休でしたので、
「シャンタラム」という超ド級の長い小説を読んでおりました。
文庫本で3冊、都合約1800ページに及ぶ大作で、
著者のグレゴリー・デイヴィッド・ロバーツの私小説であり、
加工されているとはいえ大筋は実話に近いという内容です。
舞台はインド第二の都市、ムンバイ(ボンベイ)から始まります。
作者ロバーツさんは(実際に)ニュージーランドの最重要の指名手配犯です。
麻薬・強盗などの罪で重警備刑務所で服役中に脱獄(!)し、
インドに流れ着いた、そのあたりから物語は始まります。
そしてどんどん、ディープ・インドに導かれていくのですが、
ムンバイがまだ「ボンベイ」と呼ばれていた頃のディープ・インドをご紹介します。
インドの人身売買
主人公(著者)はあるキッカケで、インド人のガイドから人身売買のマーケットへ案内されます。
迷宮のような入り組んだ先にあるマーケットでは、子供が数人立たされており、
著者は強烈な罪悪感に襲われます。
「自分が買って、開放したい」
「なぜこんな残酷なことが・・・」
そんな著者にガイドは説明します。
「この子たちは、災害や戦争、飢饉が発生した地域から、買付人がうかがって買い取った子供たちです。
そのような場所では、親兄弟、親戚が毎日毎日死んでいきます。
売るものも、食べるものも無いからです。
だから買付人が行くと、親は神様が来たかのように喜びます。
当面の現金が入るのと、この子たちが生き残れるからです。
何はともあれ、生き残れるんですよ」
インドの臓器銀行
またある時は「臓器銀行」と呼ばれる場所へガイドが案内します。
そこは病院のような出で立ちで、中には憔悴しきった老人たちが大勢ベットで寝ているだけの施設でした。
すると医者のような男が患者に番号の付いた札を張っていきます。
その番号が意味することは、「この人間の使える臓器の数」とのことです。
来るときが来たら、臓器を与える為に死ぬのです。
またもや著者はキツイ現実を突きつけられ、モラリティが揺らぎます。
「なんでこんな事が・・・」
するとやはりガイドが、何でも無いことのように答えます。
「この人たちは全員、ある病気で直に死ぬことが決まっています。
でもブローカーからここを紹介してもらい、自分の意志で臓器を提供することを決めたのです。
誰かを助けるため、家族の生活のため、ここに来たのです」
もちろん、人身売買も、臓器銀行も、当時から「違法」でした。
しかしながらインド人の徹底した合理性(それは法よりも秩序を重んじます)に自身の価値観が揺さぶられます。
インド人の価値観
法よりも秩序を重んじる、そんなインド人の性質を現したエピソードを紹介します。
インドの電車はご存じでしょうか?
ギュウギュウ詰めにされ、荷物は天井に乱雑に置かれ、電車の上にも横にも乗せれるだけ乗せて走るあの光景です。
当然、電車の中に入るのは至難の業です。
押し合い、へし合い、殴り合い、血が出ることも日常茶飯事で、まさに喧嘩しながら乗車にこぎつけるのです。
しかし、一旦電車が発車したら、ものすごくフレンドリーになるのです。
それは「色々あったけど、もう電車出ちゃったし、目的地までは仲良くしようよ」
「色々あったけど、目的地まではずっと一緒なんだから、快適に皆で過ごそうよ」
という合理性(!?)から、ものすごく車内は平和になるらしいです。
如何でしょうか。
なんとも現代日本人には考えられない、「まあ、そりゃそうだけど」と言わざるを得ないエピソードでしたが、
ちなみに日本は太古から原則人身売買は罰せられましたが、寛喜の大飢饉のときだけ、合法になった経緯があります。
その背景はインドと似たようなものです。
エイチツーは当然法は守りますが、同時に秩序も重んじております。
担当者様の背景を重んじますので、ぜひ「いろんな事情」をお聞かせください。
そこらへんの「マニュアル化」された対応しかできない大手さんとの違いが、我々の強みです。