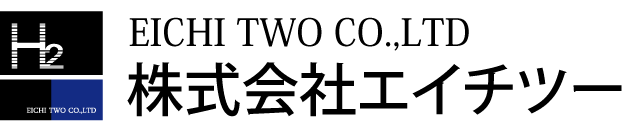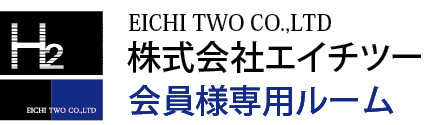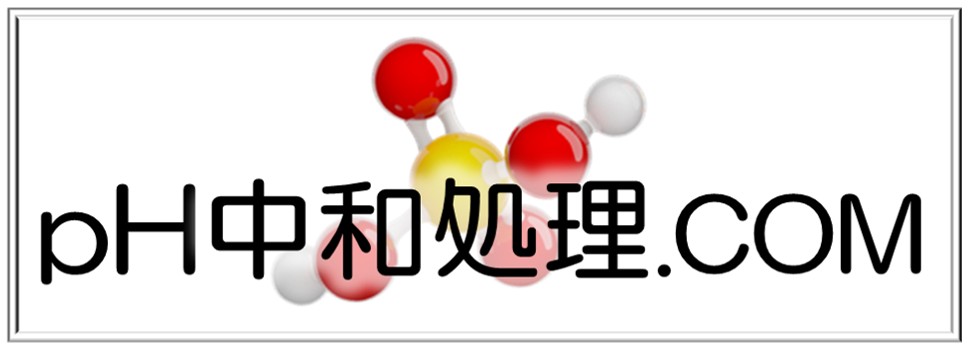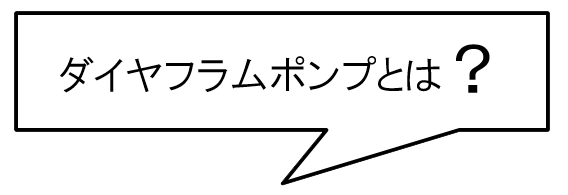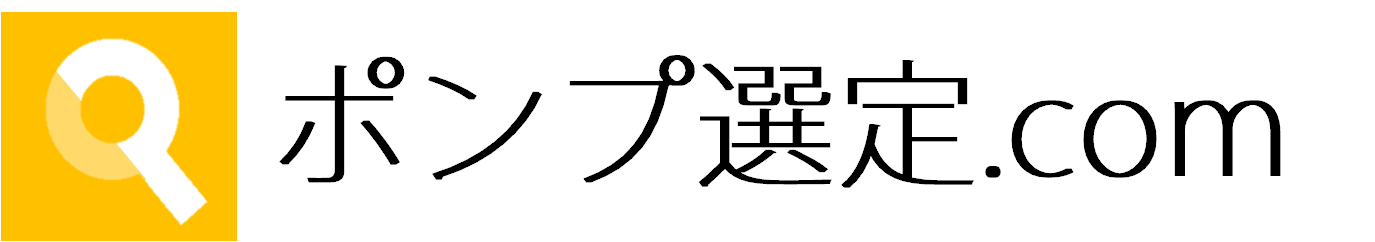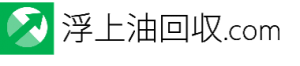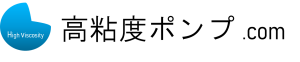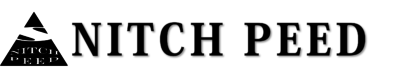From, 山田
「熱いものが苦手で、フーフーしないと飲めない…」
そんな人を指して使われる言葉が 猫舌。
実は私も猫舌で熱いものが食べられないのです。
でもなぜ「猫舌」というのでしょう? 本当に猫は熱いものが苦手なのか?
ちょっと気になりませんか?
「猫舌」という言葉の由来から猫の生態まで、ちょっと調べてみませんか?
猫舌の由来
「猫舌」という表現は江戸時代にはすでに使われていたと言われています。
理由はシンプルで、
「猫は熱い食べ物を食べられない」
という昔からの観察が元になっている説が有力です。
実際、猫は野生時代から
-
体温より高い食べ物を好まない
-
食べ物をあまり噛まずに飲み込む
という習性があり、熱すぎる食べ物は物理的に苦手。
そのため、熱いものが苦手な人 = 猫のような舌 = 猫舌 という比喩表現になったと考えられているようです。
本当に猫は熱いものが苦手?
これ、本当のようです。
猫の口腔内は、急激な温度変化に弱いと言われており、あたたかい食事でも 人間が「少しぬるい」と感じる40℃以下 が適温とされています。
熱すぎると…
-
舌をやけどしやすい
-
においの感知が落ちる
-
食欲不振につながる
といった問題があるため、猫の食事は基本的に「常温〜ぬるい」 がベストなんだとか。
つまり「猫舌」という言葉は、ちゃんと猫の特徴に根拠があるわけなんですね。
いわゆる「猫舌」は「舌そのもの」ではなく反射の問題
実は、人間の猫舌は舌の構造が猫のようだから・・・ではありません。
熱いものを口に含んだときの
-
温度センサーの反応の強さ
-
熱さを痛みとして感じる速度
などの「感覚の強さ」が人によって違うため、熱さに敏感な人を便宜的に「猫舌」と呼んでいるだけで、生理学的な意味で猫と同じ特徴ではないのです。
つまり人の猫舌は「舌の構造」のことではなく「熱いものへの感受性」の問題なんですね。
たしかに言われてみれば熱い食べ物を口に入れたときの「熱い!」という感覚は「痛い!」に近いような気もします。
なぜ猫舌になるのか?
なぜ人が猫舌になるのか?という理由は、科学にいくつかの要素が絡んでいるそうです。
1. 舌の温度センサー(熱受容体)の敏感さ
舌には熱さを感じる温度センサー(熱受容体)があります。
人によってこの感受性は異なり、敏感な人はほんの少し熱いだけでも「熱い!」と感じやすいため、自然と猫舌になるようです。
2. 口内の神経反応の強さ
舌だけでなく、口内全体の神経の反応も関係しているそうです。
-
舌の温度を脳に伝える神経が過敏な人
-
熱い飲食物に対して「やけどする前に反射的に避ける」反応が強い
これも猫舌の原因の一つ。
3. 習慣や経験の影響
-
幼少期から熱い飲み物や食べ物をあまり口にしなかった
-
無理に熱いものを食べる習慣がない
こうした経験の少なさにより、舌や口腔が熱さに慣れず敏感になりやすい。
私、心当たりがあります。子どもの頃から熱々の食べ物は必ず冷ましてから食べていました。熱いものを食べ慣れていないんですよね・・・。
4. 舌の表面の構造や唾液量
舌の表面にある味蕾の密度や唾液の量によっても、熱の伝わり方が変わるそうです。
唾液が少ないと熱が舌に直接伝わりやすく、熱さを強く感じることがあります。
あなたは猫舌ですか?それとも熱々のラーメンをズズっといけるタイプでしょうか?
猫舌でも使えるエイチツーの耐熱水中ポンプ
日常では熱すぎるものは避けることができても、産業の現場では熱い液体や高温水を扱わざるを得ないことがありますよね。
ここで頼りになるのがエイチツーの耐熱水中ポンプです。
-
高温の液体でも安心して移送可能
-
95℃の高温環境にも耐えられる
-
長時間の運転でも安定した性能を発揮
猫舌の私たちが熱さに困るように、現場で高温水移送に悩む方にも、安心して使える製品です。
製品ラインナップ